|
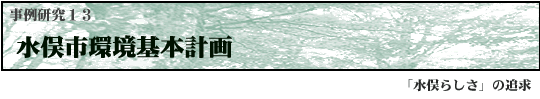
水俣市は、ごみの21分別をはじめとし、環境マイスター制度やごみ減量地域女性連絡会議の活躍、環境学習修学旅行の受け入れ、水俣エコツアー、ISO14001の取得など環境先進都市としての取り組みを進めているが、その根底にあるのは世界で類をみない公害病を経験し、それによる地域の断絶を克服していったという過程であろう。一時期は地域でタブー視され、言葉を出すことさえはばかられたこの悲惨な経験にまず向き合い、語り合うところから、地域再生のための新たな挑戦がはじまったという。そこで水俣市民が選んだのは「環境」というキーワードであった。
「水俣市環境基本計画」は、随所に「水俣らしさ」のあふれた20ページほどの冊子である。水俣市はこの計画をローカルアジェンダと位置づけ、「水俣の海・山・川を守り伝え、共に生きる暮らしの創造」の実現に向けて市はもとより、市民や事業者が一体になって行う施策をあきらかにしたものとしている。
 
 
 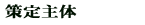
 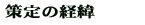
| |
水俣市では、水俣病の経験をふまえ、水俣再生を「環境と健康はすべてに優先する」という視点からとり組んできた。平成2年から「環境創造みなまた推進事業」を展開し、平成4年には市議会において「環境健康福祉を大切にするまちづくり」を、市では「環境モデル都市づくり」を宣言し、平成5年に環境基本条例を制定した。このほか、水のゆくえなどの調査を市民とともに実施したほか、21分別という厳しいごみの分別にとり組んできた。このような環境行動の実績を踏まえ、平成8年3月、環境基本計画を策定した。
|
平成3年 3月
|
|
「寄ろ会Ⅰ」で地域づくりに関する住民の話し合い |
|
11月
|
|
寄ろ会みなまた「水俣地域資源マップ」の作成 |
|
11月
|
|
「寄ろ会Ⅱ」で地域づくりに関する住民の話し合い |
|
|
|
|
|
平成4年 6月
|
|
「環境、健康、福祉を大切にするまちづくり宣言(水俣市議会)」 |
|
11月
|
|
「環境モデル都市づくり宣言(水俣市)」 |
|
平成5月 3月
|
|
水俣市環境基本条例の制定 4月 庁内検討の開始 |
|
10月
|
|
水のゆくえを調べた「水の経路図」を全地区で作成 |
|
平成6年 9月
|
|
「寄ろ会Ⅲ」で地域づくりに関する住民の話し合い |
|
10月
|
~ |
総合計画策定に関する地区懇談会(環境に関する住民意見の反映) |
|
平成7年 10月
|
|
水俣市環境審議会の設置 |
|
10月
|
9日 |
第1回水俣市環境審議会 |
|
11月
|
1日 |
第2回水俣市環境審議会 |
|
10月
|
~ |
総合計画策定に関する地区懇談会(環境に関する住民意見の反映) |
|
11月
|
29日 |
第3回水俣市環境審議会 |
|
1月
|
10日 |
第4回水俣市環境審議会 |
|
2月
|
20日 |
答申 3月 水俣市環境基本計画の作成 |
|
|
|
|
|
 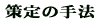
 
| |
策定段階では、地区懇談会をおこない、100回を超える説明会を実施した(水俣市総合計画を同時につくっていった)。また、若い人を取り込んでいくため、団体・職場向けのワークショップを行った。
地区ごとの「寄ろ会」による話し合いも市民参加に大きな役割を果たしている。 |
 
| |
水俣市環境基本計画は以下のように構成されている。
| 第一章 |
計画の基本事項 |
| |
改革策定の趣旨、視点、範囲、期間、市、市民、事業者の役割 |
| 第二章 |
基本方針 |
| |
水俣病の経験から |
| |
目標 |
| 第三章 |
環境施策の体系 |
| |
○水俣病の教訓を胸に |
| |
・水俣病に取り組み共存 |
| |
・環境再生の象徴づくり |
| |
・生命の尊重 |
| |
○海、山、川の保全 |
| |
・海の保全 |
| |
・再生 |
| |
・山(森)の保全・再生 |
| |
・川の保全 |
| |
・再生 |
| |
○自然と共に生きる暮らしの創造 |
| |
・環境に負荷の少ない暮らしづくり |
| |
・心を癒す住まい町並みづくり |
| |
・環境に配慮した産業への転換 第四章 計画の推進のために |
| |
・計画推進の主体 |
| |
・計画の進行管理 |
| |
・関係団体等との連携 |
| |
・財政措置等 |
| |
・環境関係情報の収集及び提供 |
| |
・広報、啓発 |
| 第五章 |
わたしたちは行動します |
| |
○環境行動の展開にあたって |
| |
・環境行動の発表の場づくり |
| |
・住民参加 |
| |
・施策の連関 |
| |
○環境行動の成果を引き継ぐ |
| |
・環境創造みなまた推進事業 |
| |
・市民の行動力の継続 |
| |
○地区ごとに行動する |
| |
・お知らせ |
| |
・環境行動の目標設定 |
| |
・地域環境協定 |
| |
○新たな行動をおこす |
| |
・環境再生の象徴の創造 |
| |
・水俣の川を守りきれいに |
| |
・環境産業の展開 |
|
 
| |
a) 地区環境協定の締結と実施という仕組み
b) 「水俣らしさ」を前面に挙げていること
c) 伝統技能・知恵の重視
d) エコツーリズム |
 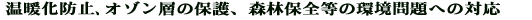
| |
温暖化防止に関しては、「自然とともに生きる暮らしの創造」の中で、「省エネルギー」の項目をもうけ、「水力、太陽熱、堆肥の発酵熱、発酵ガスの利用」を挙げている。
また、国際貢献については「計画策定の視点」として、「水俣病の教訓の伝達と活用に関する国際貢献の推進」を掲げ、人類への警鐘となった水俣病の教訓および教訓に基づいた地球環境の保全・再生の取り組みを広く日本のみならず国際社会に伝えていくようつとめるとしている。この一環として、「水俣の智恵袋」とし、お年寄り200人を水俣人材マップに登録し、水俣病について語り継いでいく取り組みを行っている。
|
 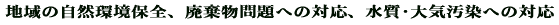
| |
廃棄物の問題への対応として、「ごみの減量化とリサイクルの促進」「分別収集の徹底・生ゴミの堆肥化推進」「廃食油、廃プラスチック類のリサクルの推進」「自動販売機の削減」「ゴミ循環の体制の充実」を挙げている。(21分別方式についての囲みを入れる)
自然環境の保全への対応として、特に「生命の尊重」を掲げ野生動植物の保護を謳っているほか、多様な生命の存立基盤の保全として「海・山・川の保全」を重要視している。
例えば自然林の保全、再生として「シイやカシ、ツバキ、クス、モミ、トガなどで山の頂や尾根筋、急傾斜地、山の中腹、奥山は自然林に再生」すること、「荒神さんのある所とその周辺は自然林に再生」することなどを掲げている。
|
 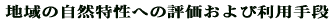
| |
例えば海の保全・再生で、「自然の渚の保全」「光の届く浅い海の保全」「埋立地などの人工護岸の多自然化」、また、自然な川べりの森の保全と回復として「川筋、谷筋の河畔林の保全(自然な川べりの地形、雑木や竹:メダケ、ホウライチク、ハチク、マダケ、柳やメツッパリ(セキショウ))」を挙げているのは、水俣の自然特性に基づいたものだと考えられる。
【環境マイスター制度】
環境や健康に配慮した物づくりに取り組んでいる市在住の大工や建具、左官、畳職人など農林漁業従事者を認定し、支援し、その知恵を地域づくりに活かしていこうというというのが水俣市の「環境マイスター制度」である。
申請後、審査を行い、有資格者と認められた者は、水俣病の基礎知識、自然生態系の仕組み、環境ホルモンなどの有害物質の基礎的な知識についてなどの講習を受けた後、「環境マイスター」として認定される。
現在、有機農法でのお茶栽培に取り組んでいる市民、漂白剤無しの紙すきに取り組んでいる市民、アイガモ農法での米づくりを行っている市民など9人が認定されている。
○制度の仕組み [申請]→[資格審査]→[環境に関する講習]→[認定]
○資格審査の基準
(1)環境や健康に配慮したものづくりを5年間以上行っていること。
(2)自然素材の利用、化学物質の除去など環境や健康に配慮したものづくりに関する実績があること。
・安心安全な自然素材の利用(輸入材木、化学素材などの住素材などはなるべく使わないなど)、近くで入手できる資源の使用など、資源調達の段階で環境や健康に配慮している。
・化学肥料、農薬などは極力少なくし、有機肥料の使用によって、環境や健康に配慮している。
・生ゴミの堆肥化、異業種間での廃棄物の利用などによって、ものづくりの段階で排出される破棄物の極小化など環境負荷に対して極力軽減する活動を実施している。
(3)環境や健康に配慮したものづくりに関する一定の知見と経験・技術等を有していること。
(4)地域環境の保全に関する活動を行っていること。 ・地域の環境保全活動に参加した経験を有している。
・その他公益的な活動に参加した経験を有している。
(5)環境問題や環境保全に関する一定の知識を有していること。
(6)水俣病など公害に関する一定の知識を有していること。 |
|
 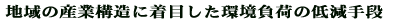
| |
水俣市が同計画に盛り込み、またその後も力を入れて取り組んでいるものとして、①エコツーリズムの推進、②有機栽培減無農薬農業の展開、③伝統知識の保全・継承・活用推進、④竹やハゼノキなど森林資源の有効利用、があげられる。これらはいずれも「水俣らしさ」の追求といった性格を併せ持っている。
エコツーリズムの推進としては、水俣環境案内マップの作成、水俣湾埋立地周辺等の観光用施設整備、案内人の育成(「語り部」制度)などを行っている。
農業関係では、現在、有機栽培のサラダ玉葱や緑茶などを健康や環境に配慮した地域の特産品として扱っている。 伝統知識の保全・継承・活用推進では現在、「環境マイスター制度」「水俣の知恵袋(水俣人材マップ)」などが実践されている。
|
 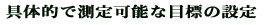
| |
同計画では、定めていないが、地区ごとに環境に関する行動目標を設定し、地区環境協定を結んで実施していくものとしている。 |
 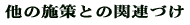
| |
この計画は水俣市環境基本条例第8条、第9条、及び第10条に定める施策の基本に必要な措置を講じるものである。
|
 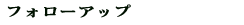
| |
環境創造みなまた推進事業などの推進と併せ、地区環境協定の締結と実施、市民の行動力の継続を行っていくものとしている。(市民団体と市、事業者のパートナーシップの例として「食品トレー廃止での調印」がある。)
|
 
| |
水俣市福祉生活部環境課環境保全係
熊本県水俣市陣内1-1-1(〒867-8555)
Tel.0966-63-1111 (内線165) Fax.0966-63-9044 |
|