ホットレポート①森の視点から、人の世を詠う 熊谷龍子の最新歌集『葉脈の森』を読む
2020年04月15日グローバルネット2020年4月号
エッセイスト
乳井 昌史(にゅうい まさし)
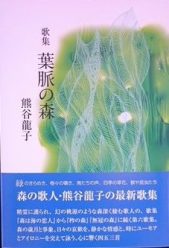
『葉脈の森』(遊子堂、2400円+税)の表紙
奈良・興福寺の寺報「興福」の最近の号の巻頭言を読み、うなる思いをした。宿願の中金堂再建を成し遂げた多川俊映師が、「貫首」から「寺務老院」へ立場が代わっても筆を執っているのが嬉しく、本質を衝く論調とわかりやすい表現にうなずかされた。
「やはり、自然の中の人間だ」と題して自然災害を招いている現実を思い、「『自然と人間』にしろ『人間と自然』」にしろ、私たちはもうそろそろ、そうした対立構造を捨てる時期に来ている」と二項対立的思考の限界を指摘し、「自然の中の人間」というスタンスを取り戻そうと訴える。「自然をコントロールできる」妄想を戒め、熊谷龍子氏の『葉脈の森』の一首に着目し、「〈森林浴〉という言葉あり 毎日を樹に囲まれている我は好まず、というのを見つけた。この歌人は森を対象化なぞしていないのだ」と結ぶ。うわべは自然と対等の関係を装いつつ、人間主体にこだわる風潮に警鐘を鳴らさずにいられなかったのだろう。
名刹の僧にそう思わせた歌人こそ、山に植樹して豊かな海を取り戻す運動に弾みを与えた、あの「森は海の恋人」の作り手なのだ。三陸漁師の畠山重篤氏に懇願され、森から海へ通って得た代表歌〈森は海を海は森を恋ながら悠久よりの愛紡ぎゆく〉から、こぼれ出るようにキャッチフレーズが生じたのである。
◇
僕が歌人を知るようになったのは、〈……愛紡ぎゆく〉を含む『歌集 森は海の恋人』を手にしたお陰だろう。『柞の森』『無冠の森』などを経て『葉脈の森』は、第六歌集となる。〈靄ひきて手長野をしずかに浸しゆく太古の頃の夜明けのように〉と詠む宮城県気仙沼市の山寄りで龍子さんは、中央歌壇にも聞こえた祖父らの足跡を辿りつつ森と交歓してきた。ナラやクヌギ、カシワを指す古称、柞の森の原風景を想起させる空気感に浸ると、実にまあ、気持ちがいい。
〈何処までも瓦礫の連なり それでもなお巡りの山野、緑増しゆく〉。東日本大震災の被災地詠も収録されているが、どの歌にも連綿と培われてきた風土への愛がある。〈千年に一度の揺れを体感す 誰も追体験できないように〉は、岩手県北上市にある日本現代詩歌文学館が企画した「明日から吹いてくる風――2011.3.11と詩歌、その後」展への出品作。たまたま訪ねていて色紙と向かい合った僕は、スケール感と奥行きのある詠誦に心中深くゆさぶられた。
自然との共生を志向する歌人は、『葉脈の森』でその傾向をいっそう強めているが、自在感も増している。そこで今回は、こちらも思うままに言葉を連ねてみよう。自在とは、とても言えないまでも。
〈採り立てを海水であらい食したる彼の夏の日の格別の海鞘〉。畠山さんに「森の妖精を思わせる」と評された歌人は、ホヤ好きなのか。これはしかし、癖のある魔味へ迫るに最適の食べ方だろう。鋭さと円熟を兼ね備えた当代の俳人、正木ゆう子氏の〈海鞘切れば海ほとばしる刃先かな〉の句と好一対の出来。龍子短歌には「……〈海鞘〉食めば口中に海は広がる」の一節もある。僕の郷里の青森も産地であり、帰省すると鮮度を損なわないようにして待ち構えてくれた父と明るいうちに向かい合う。天然の吸い物みたいな汁で口を湿してまず酒を一杯、それから刺身へ。「どうだ?」と聞くので「旨い。最高の肴だ」と答えると相好を崩して笑う。父親と息子、ぶつかり合う面も残している頃だったが、酒杯を介して親孝行の真似事ができたのは幸せだった。ホヤよ、ありがとう!
◇
自在と言えば、今度の歌集には〈遠慮がちに控え目に季を窺うように遠近自在に梟啼けり〉も収められている。哲学者みたいなフクロウの風貌が気に入っているそうだが、時季や遠近の状況に応じた声の出し方にも惹かれているのかもしれない。季節感の危うさを伝えるような沈黙、如月の満月の夜に初めて声を聞いた時の安堵感……。悠揚迫らざる留鳥の生態を描いた歌の味わいは格別だが、たまたま出かけた東京・井の頭自然文化園で物した「立夏の森」の項のフクロウ数首の詠みぶりからは、掌編小説の連作集を読んでいるみたいな自在感が伝わって来て興味深かった。
手長野のフクロウが啼かないのを気にしながらの上京中、自然文化園の檻の中で声も出せないフクロウに気づき、〈こんな処におまえは居たのか 柞の森の梟に不在の夜が続きて〉と問いかけ、〈真夜中に鍵を外して羽広げ戻っておいで 柞の森に〉と呼びかけた一連は、〈自然文化園訪いしより丁度一週間 柞の森に梟の声は戻りて〉と結ばれる。いやあ、面白い。これを、そんなことあり得ないよ、と言っては身も蓋もない。フクロウから羽を借り、創作の翼を思いっきり広げようとしたのだろう。連作形式で、三十一音の短歌表現の枠を越えようとした試みにも思える。
吉祥寺行の目的は自然園ではなく、実は娘を訪ねることにあった。〈こんな処に系譜はいたんだ 吉祥寺北町に住む娘の男の子〉。歌人のエッセイ集によると、「みちのくから私が訪ねて行ったらドアを開けてくれた幼きもの」に系譜としての孫を実感したという。娘の自立が続いた当然の流れとはいえ、〈吉祥寺 苗場 山形 気仙沼 この夜家族は此処におります〉という風に展開する。これから孫たちとの関わりが、作品群にどんな変化をもたらすだろうか。〈沁みじみと異空間に居ると思いおり 薬袋まで管理されいて〉など病床詠もあるのに気づき、自分の置かれている状況と重ね合わせ、今まで以上に身近な存在に感じられた。淡々と受け容れる詠みぶりに励まされる。
◇
自分の好みでホヤやフクロウの話へ傾いたようなので、もう少し系譜について綴ろう。歌集に表れた系譜の焦点は孫たちにあるが、さかのぼると、手長野で家業に励んだ龍子さんの父親や祖父らに行き当たる。祖父の熊谷武雄は、前田夕暮主宰の「白日社」同人として歌作を続け、結社誌「詩歌」の創刊当時から活躍した。林業に従事しつつ山村の生活感や自然観を詠った歌人として知られる。その武雄が就いた前田夕暮と言えば、明治四十三年に歌集「収穫」を発表し、同じく「別離」を著した若山牧水と「比翼詩人」と並び称された。「明星」と「アララギ」の全盛期の間のいっ時だが、「牧水・夕暮」時代を画したのである。
牧水が主宰した「創作」の同年三月号を見ると夕暮はむろん、白秋や啄木、哀果(善麿)、晶子ら豪華な顔ぶれが寄稿しており、その中に若書きと言ってもいい武雄の青春詠がある。〈我しらず少女の群に逢へば先ず似たる面わを求めけるかな〉。歌壇事情に通じている訳ではないが、論争しつつも交流した時代の痕跡を感じる。結社間、散文や詩歌・俳句などジャンル間の垣根が今より低かったのかもしれない。
今年も花の季節が来たか、と思ったら『葉脈の森』の中に梅と桜を同時に咲かす東北の佐保姫を詠んだ一首を見つけた。花ばかりか、〈ふきのとうみつばたらのめうどこごみたけのこわらび わっと山菜〉のリズムにもワクワクする。歓喜の歌。みちのくに育った者としては、山野に開く何もかもが一斉に上げる声にゆさぶられるようで嬉しくてならない。
〈他所の桜華やかなりしと思えども我が窓の映す山桜愛し〉〈一年振りの筒鳥の声 我が森の冬のベールはいま外されて〉――。おや、同じページに並んだ山桜と筒鳥の歌、これは牧水の愛したもの二題ではなかろうか。僕の好きな旅ゆく歌人と森に暮らす歌人は、時代も日々の営み方も異なるが、自然へ没入してそこから言葉を紡ぐ短歌作法には似たところがある。祖父の代から結びつきのある夕暮を介した牧水との不思議な縁。そう思うと、これから先は時空さえも超えた大きな広がりの中で、龍子短歌を鑑賞できそうな気がして読者としては楽しみである。
